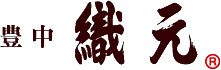染と織のコト
長野県飯田市に廣瀬さんの工房をしばらくぶりに訪ねた。
6月であっても雪を冠するアルプスの峰々、清流で名高い千種川、大阪から訪れるたびに澄んだ爽やかな空気に肺の隅々までが浄化されていく。
美しいこの街は寒暖の差が大きく養蚕に適した土地といわれ、
明治以降絹を中心とした産業がたいへん栄えたという。
弊社の女将の故郷でもあり、ちいさいころに赤い桑の実を食べた思い出を時々話してくれる。
飯田紬といわれる素朴な味わいの裂は筆者の知る限り、現在では廣瀬染織工房だけで織られているもので、やさしい色合いとその生地感が他に類をみない。
手触りはふっくらとしてしなやか、艶があり、柔らかな光をたたえるような、、、なんとも美しい裂なのである。
ご自身のことはあまり語られないが、時折出てくる会話をつないでみると、お父様の代では多くの製品を扱い、手広く経営していた。
一方、ご自身はいわゆる大量生産品を少しずつ減らして、ほんとうにいいものを織ろうという思いをぶれずに経てきた。
現在はきもの地のみだが、力織機を使って胴裏などの裏物まで織っていたときの話を伺った。
より良い製品をつくろうと試行錯誤して、それまでにない、きものによく添うしなやかな胴裏をつくった。しかし、問屋の仕入れ方に見せると、こんなのはダメだという。当時は見た目が大切。均一でフラットなまるで紙のようなものが求められ、工夫して改良した点が全く評価されない。「悔しいというか情けなかったね。」
とにかく、見た目がよければいい。ものがいいとか、着やすいとか、ではなくパッと見た目さえよければいい。きものでも同じだった。
本来目利きでなければならない仕入方のプロが、全て効率、効率で考えてしまうからおかしくなってしまう。そんな経験も廣瀬さんのものづくりに生かされているように思う。
廣瀬さんの機を見せてもらうと、経糸が見たこともないくらいたるんでいる。
つまりルーズなのである。経糸にテンションを掛けないで緯糸を入れていく。ピーンと張った状態ではないから開口も大きく開けられるわけではない。当然、緯糸を入れる杼のペースはゆっくり。トン、トントン、トン、トントン、と筬を打ち込む。リズムよく繰り返されながら緯糸がギュシィ、ギュシィと鳴って入っていく。ゆっくりなのである。
「私もずーと主人と織っているけどね、この人みたく上手にはできないね。」極めて上手な織り手である奥様はとなりの機で、笑いながらそう夫のことを評価する。
「お客さんをがっかりさせたくない。もうその思いだけだね。僕の織ったきものを着たときにお客さんに「きものってこんなに着にくいものなの?」と感じて欲しくない。」
そのためにはどんな糸を使い、どんな染料を使い、どう織るのか?考え続けてきた。
廣瀬さんの到達点は、糸に過剰なテンションをかけず、無理をさせない布なのだ。
廣瀬さんのコトバを借りると「絹の豊かな凸凹感と、蚕が描きました8の字のカールを生かそうと、やさしさと空気を織りこもうとゆったりと手織りした。」のである。
それは均一性とか効率性といった、今多くの分野で求められている観念とは全く逆の方向だろう。
いろいろな迷い道に入りこんだとき会いたくなる。廣瀬さんとその裂は私にとってはそんな人であり、モノのように思う。