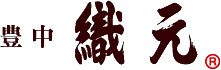染と織のコト
型を使って染める『型染め』のきものや帯は、連続する柄の楽しさや精緻さが魅力と言われる。
京都のKさんが手がけている染めのものは『型染め』でありながら、ちょっと違う魅力を放っている。
3代目になるKさんとは先代のころからかれこれ20年以上のおつきあいになるが、合うたびにどこか奥の方の引き出しから面白いものを出してくれる。
普段は仏光寺近くの事務所で会うことが多いのだが、数年ぶりに山科の工房をたずねた。
型染めは生地の上に文様にしたい柄を彫った型紙を置いて染めていく技法だ。
50センチほどの幅、7メートルほどの長さの平らな板に白生地をピーンと固定する。型の位置を定めて、幾種類もの刷毛やへらを染料やのりによって使い分けて染める。型の場所をかえて、また染める。型をかえ、色をかえ、刷毛をかえ、これを繰り返す。
良く知られていることだが、板場とよばれるここの現場は過酷だ。
この空間は乾燥を避けるため、冷暖房は使わない。床は土間だから冬はしんしんと冷え、夏はとても我々は入っておれないほどの暑さになる。
次の工程に行く前に生地を乾かせるため7メートルもの板を頭上に垂直に持ち上げなければならない。40数キロもある平らな板を1メートル以上もである。
板を上げたり下ろしたりする作業は一日に40回も50回も繰り返すという。(それで最近まで女性の職人は皆無だったそうだ。)
「どのくらいやってるかって?
大分から集団就職でね。金の卵とかいわれてね。でも周りは、つらくて3ヶ月でほとんど帰ってしまいよったね。当時はみーんな厳しかったから。朝から晩までずーと働いてたからね。
いまではこの人しか、まずできんやろ。という名人。複雑な仕事を正確に仕上げていく。
それに加えて厳しいのは色のことだ。
Kさんたちは色にとかくうるさい。
現場を預かる大将は先のKさんのお祖父さんのころから、とにかく親父たちはずーと議論していたことを懐かしそうに話してくれた。
「長い時は一日10時間。柄と色で喧々諤々ですわ。ぼくも勉強やと思って横で5時間は辛抱してましたけど、、、(笑)イメージをつかむまでがとにかく大変やったね。ぼくらもそんな色やったらアカンって、そらもう毎日ですわ。それでね、晩年は親父とは、『もうそろそろ秋向けに、あの柄をあん時の色でやってくれへんか。』ってね。“あれ”“それ”通じるんやからね。そらもうすごいもんですわ。」
両方を良く知る大番頭のHさんは懐かしそうに話してくれる。
「僕みたいに、現場を知ってると壁をつくってしまうんでしょうね。この柄は彫るんがむずかしいな、とかきものにしたら大きすぎる柄やろ、とかね。でもきもののこと知らんというかあえて知らんようにしてたのか、、、トルコやらオーストリアやら行ってきた時の向こうのお菓子の包み紙や、お土産のパッケージで、この柄作れとか、この色にしてやー、ってね。今から考えても、ものすごう発想が自由やったですね。」
先達が取り組んだ、頭と頭を突き合わせ、悩みぬいて取り組んだ職人と作り上げた関係は、それこそが最大の財産だったようだ。気脈を通じあうなかから生まれる妥協のない色彩は、時代が変わってもとどまることなく洗練され、自由な発想による柄が伸びやかに現出する。
Kさんたちによって生み出される型染めは新しい魅力にあふれている。
「僕らはね、10年たって、20年たっても、お客さんがたとう紙をあけて時に、ああええ色やねって言ってもらえる。そういう仕事がしたいんです。」お会いするたびにいつも先代が話してくれた言葉と笑顔を思い出した。