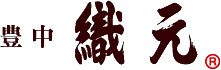染と織のコト
京都の西に染の技師の松江さんを訪ねた。
京都のきもの、とりわけ京友禅といわれる染めものに携わる人々は、染上がった美しい裂と同じく、複雑な仕組みである。
職人をたばねるのは悉皆屋さんである。
悉皆屋さんは、タクトを振る役割。
それぞれの技師たち人材の配置を決めフォーメーションを組み、ときには激しい相克や葛藤がありモノを作り上げていく。
とりわけこのタクトを振る人物の力量が作品の良しあしを決する。それは、知識とかセンスとか段取りのよさ、あるいは人としての魅力のようなものも含まれるのかも知れない。
人を動かし、やる気にさせ、持っている力以上を引き出す。
優れた演奏者たちを調和させて、観客の心に響く裂を奏でるのだ。
数年前に亡くなった悉皆屋さんの英之助さんは松江さんのことを称して、「あんたのとこは、けれんもん屋やな。」と話したという。外連味(けれんみ)のない というのは「はったりやごまかしがない」という意味なので、「けれんもん屋」というのは「はったり、ごまかしがある様。」か?あるいはいい意味では「何でも器用にできる。」というような意味だろうか。
松江さんが手がけるのは、木版染である。
御自宅の1階に工房がある。明るい部屋。使い慣れた作業机まず、作業板の上に生地を固定する。染料をフエルトのような布に筆を使ってまんべんなく塗り、その上に文様を彫った木版を置く。染料が載ったタイミングをみて、生地にハンコを押すようにしておいていく。木版の染は概ねこの繰り返しである。
松江さんは右手でリズミカルに迷いなく置いていく。
まるでその場所に定められているように、一直線に。
フエルトに行き、正しい分量の染料をもらい、生地に行く。
正しい場所に正しい時間とどまり、また、フエルトに向かう。
80回を少し過ぎたところで、二尺程を染終わった。全くズレがない。
「このくらいできるようになったらまぁあとは同じでしょ。」
「そこまでがなかなかできるようにならへんのよ。」と横から奥様。
夫の仕事を自然に手伝うようになり、こうした高度な技も身につけて今では奥様の方が得意なのだそうだ。
このお二人の息の合った器用さが、悉皆屋の御大をして「けれんもん屋」と言わしめた、ゆえんかもしれない。
とにかく様々な注文に応じていろいろなことに挑戦してきたそうだ。
きっと御大は松江さんならここまでやれるだろうと、その人柄と腕を見抜いていたにちがいない。
「ほめられたんかな?どないやろ?」と松江さんは笑っている。