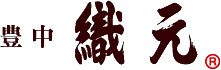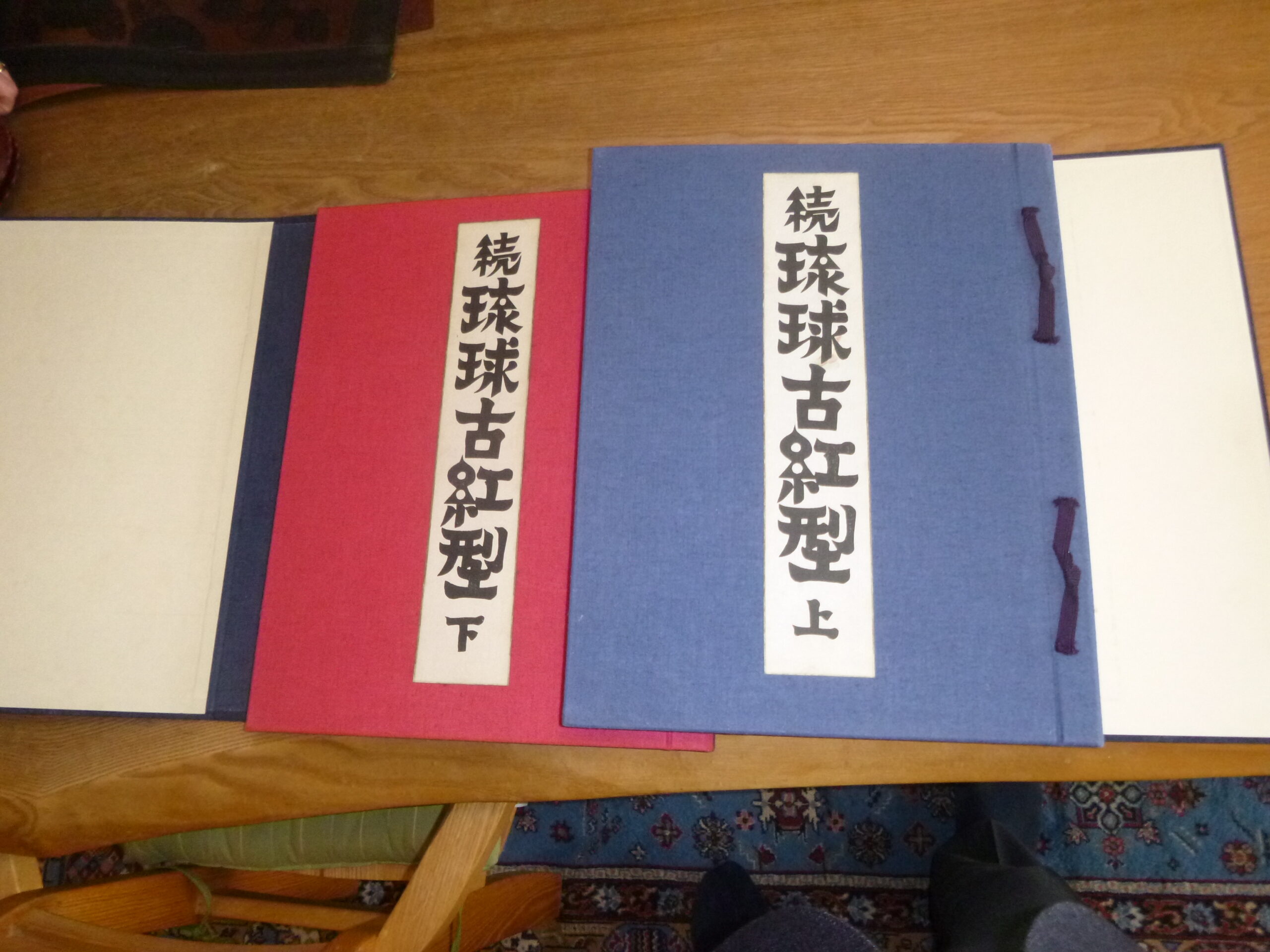型絵染 荒川真理子さんの仕事
1952年生まれ 荒川真理子
とある展覧会で見た作品の素晴らしさに魅かれて、少しずつ作品を注文していた荒川真理子さんの水戸市のご自宅兼工房を訪ねました。
野趣っぽいダイナミックな文様も、艶やかな花柄やリボンを配した可愛らしいデザインも荒川ワールドの世界に入ると、やっぱり荒川真理子さんらしいね。となって魅了されてしまいます。いったいどんな魔法?があるのでしょうか?
「型絵染」は作り手の着想を文様化し、和紙に型を彫る。生地を選定し、型を据えて糊を置く。彩色し再び糊伏せをして地色を引く。すべての工程を一人で行います。
どの工程も作り手その人ならでは、のやり方がそれぞれにあるのですが、
少し大雑把にいえば、作者ご本人らしい創作的な作業は、1.着想から文様化すること2.色を置くことの二つといえます。その一方できものや帯の衣としての魅力はデザインに加えて、その工程ひとつひとつをどれだけ丁寧に積み上げるかといういわば職人的な要素にかかっているといえます。
荒川さんはそれぞれの工程を高いレベルで確立し、どこにもない荒川真理子の作品を作り続けています。
ある帯を前にお話を伺いました。
「この帯は、もともと更紗っぽいのを作ってみたくて型を彫ってみました。大きくしてみたり、横に並べてみたりして、私は紅型も好きで取り入れてみたりしています。
母のきもので、いろいろと古くても素敵なのがあるんです。 そういうのは大好きなんですけど、それにはどんな帯がいいかなって考えながらつくります。こんなふうな帯だったら母の濃藍の結城なんかに合わせても素敵なんじゃないかなって。。。
結局、きものにしても帯にしても自分で着たいって思えるものを作っているんだと思います。」
「絵本をつくるのが私の最初の夢だったの。それで女子美のグラフィックデザイン科に行こうと思って、見学に行きました。
そうしたら、柳悦孝先生でしょ、柚木先生でしょ、それでその日に志望を工芸科にかえました、入学してからは、本当に厳しかった。大学っていうよりは職業訓練校でした。
課題を寝ないでやるってこともしょっちゅう。
でもほんとうに楽しかった、柚木先生の授業がとにかくおもしろかった。だから型絵に進んだのね。」
鮮やかな色が主張しながら調和して戯れて、観ている人も着ている人も楽しくなるような荒川さんの作品がもつ真髄を垣間見たようなお話を伺いました。いっそう次回に届く作品が楽しみになってきました。